3月は寒さが緩み始め、木の芽は膨らみ、地表では元気よく「つくし」や「ぜんまい」が顔をのぞかせてきます。

また私たちの身の回りの生活面では「卒業」「退職・引継ぎ」にともなうお別れの月であったり、転職・入学などに向けた引っ越しや・初めての一人暮らしなどの、何かとあわただしくなってくる月でもありますね。
このページでは3月といえばで思いつく、あるいは3月にまつわる色々な事柄を集めてみました。
知っているようで知らなかった3月のあれこれ・・みなさんもぜひこの機会に振り返ってみてはいかがでしょうか?
3月の別名や語源
我が国では旧暦の3月を『弥生』と呼び、現在でも新暦3月の別名として用いていますね。
「木草弥や生ひ月」・・これが短縮して「弥生」と表されるようになったという説が有力なようで、木々や草々が生まれる(芽吹く)月という意味から来ています。

「弥」=益々・いよいよ
「生・おい」=草や木が芽吹く
きくさいやおいつき⇒いやおい⇒弥生
その他の3月の異名・別名
『晩春』=旧暦では1月から3月までが春とされていたことから、春の終わりの月という意味。現在の暦では5月頃です。
『暮春』=「晩春」と同じ意味。
『花月』=「桜月」「早花咲月」「花津月」などの異名とともに、長かった寒い季節が終わりやっと咲き始めた”花待ちの月”、との意味合いがこめられています。
『夢見月』=室町期の歌書『千金莫伝抄』に伝えられている表現で、桜に代表される春に咲くはかない花のイメージが、「霞」・「まどろみ」・「朧」などの春(3月)が持つイメージと重なり、「夢を見る様な月」『夢見月』と呼ばれるようになりました。
英語の3月『March』について
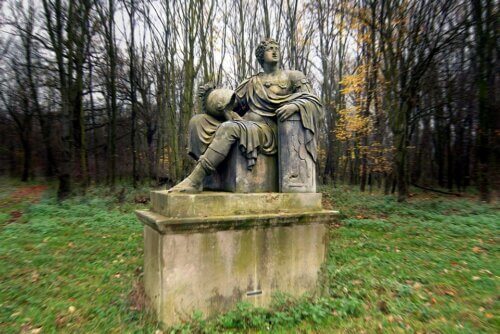
ローマ神話の神・マース(Mārs)の名前にちなみます。
古代ローマでは1年の始まりの月は3月とされていました。マース神はローマ神話では主神級の扱いを受けていて、1年の始まり3月の守護神とされていたそうです。またその神格も「軍神」「農耕神」であったことから、寒さが和らぎ戦いが可能となりはじめる時期、草木が芽吹き農耕が盛んになりはじめる時期、3月のイメージにピッタリと当てはまっていますね。
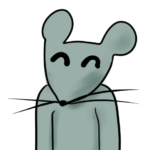
マース神は「マルス」「マーメルス」とも呼ばれていたり、異名としての「軍神グラディーウゥス(Gradīvus)~進軍する者~」があるよ。
なおKONAMIのシューティングゲーム「グラディウス」の語源は、ラテン語の「剣」(gladius)を意味する言葉だそうだよ。
『↑↑↓↓←→←→BA』⇇素敵な呪文だね♡
3月の暦・祝日
3月3日:雛祭り(ひなまつり)・桃の節句(もものせっく)
女の子の健やかなる成長と将来の幸福を願い、天皇皇后両陛下に見立てたお内裏様とお雛様を「雛飾り」として飾る日・・これを一般的にひな祭りと呼んでいます。

正式には「桃の節句」「上巳の節句」と呼びます。
| 五節句名 | いつ | 縁起の植物 | 縁起もの |
| 人日 | 1月7日 | 春の七草 | 七草がゆ |
| 上巳 | 3月3日 | 桃・よもぎ | 白酒・ひなあられ |
| 端午 | 5月5日 | 菖蒲 | ちまき |
| 七夕 | 7月7日 | 竹・笹 | 瓜・そうめん |
| 重陽 | 9月9日 | 菊 | 栗ご飯・菊料理 |
ひな祭りに「人形」が飾られる理由は、大きく三つの由来から来ているそうです。
①古くから宮中に魔除けとして祀られている「男女一対神」が「ひいな・ひひな」と呼ばれていて、これが「人形飾り」の原型とされています。
②「源氏物語」文中にも登場する、公家社会の十代を迎えるまでの女児の遊びで、藁や紙で人型に模った「人形」を用いる「ひいな遊び」が存在していました。
③古来我が国では、時として人に襲い掛かる災難や病魔を祓うために木偶(身代わりの人形)などに「厄・禍」を依らせ、それを川に流したり、お焚き上げをしたりして「祓い」・「身の清め」としてきました。
「草人型」はその典型例で、等身大の人型像を作って道端に飾り、厄除け・禍除けなどの身代わりとしたもので、その由来は三韓征伐で有名な「神功皇后」にまで遡ると言います(後に人形は小型化)。
「天児」や「這子」は子供により特化した身代わり人形の事で、子供が生まれてすぐになどに、その子が本来背負うはずの「厄・禍」を人形に移し祓いとしてきました。
と、いう事で・・
- ①男女一対の厄除けの神としての「ひいな」
- ②人型人形を用いた女児の遊びとしての「ひいな遊び」
- ③「草人型」「天児」「這子」としての「身代わり人形」
この三方面のゆかりが時代が下がるごとにうまく融合し、こんにち的な人形を飾り立てる「ひな祭り」となっていったとする説が有力なようです。

人形の歴史は古いそうですけど・・今みたいな「ひな人形」が生まれたのは室町時代の中頃なんだそうです。

あとね、お人形を何段にもかざるのは”えど時代”からで・・はじめは三段くらいだったそうですよ。
七段かざりがつくられたり、みんな(庶民)にも「ひな祭り」が広まったのは”えど時代の中ころ”からなんですって。
参考記事⏎

3月21日頃:春分の日(しゅんぶんのひ)
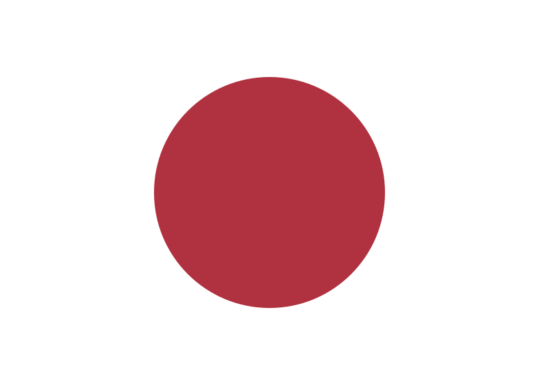
その始まりは皇宗(歴代天皇家の先祖)を祀る「春季皇霊祭」という祭日でした。
もちろん現在でも皇居内の皇霊殿において、その儀は絶えることなく引き継がれています。
こんにち一般的に、1949年より「春分の日」として法律が定める国民の祝日になっています。
「自然をたたえ、生物をいつくしむ日」と謳われています。
毎年概ね3月20日か21日に春分の日が訪れます。
そもそも「春分」とは、陰暦による季節の節目「二十四節気」の一つで、この日は昼と夜の長さがほぼ同じになり、また太陽がほぼ真東より昇り真西に沈みます。
祝日としての「春分の日」は特定の1日を指しますが、一般的に「春分」は一定の期間中を指しています。
毎年概ね3月21日頃から4月4日頃(次の節季「清明」)までが春分の期間です。
我が国は古くから稲作の周期”田起こしから収穫~次の田起こしまで”を「一年」と捉えてきました。
古代メソポタミアで発見された太陰暦(月の満ち欠けの周期)の影響は日本にも太古から伝えられたようですが、のちに日本独自の稲作文化に馴染むよう1年を24の季節に分けた「二十四節気」と、それを補う「雑節」とを取り入れ独自の暦(季節)をつくり出していたのです。
もとは戦国時代(前500~200年代)のシナ大陸の中原(黄河中流域)と呼ばれた地域の「季節を表す暦」として編み出された区分が、日本に伝わったものです。(発祥国ははっきりしていません)
二十四節気の始まりは立春で、「春分」は立春から数えて4番目の節気です。
以下二十四節気は御覧の通り。
| 旧暦月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 節季 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 | 小寒 |
| 中気 | 雨水 | 春分 | 穀雨 | 小満 | 夏至 | 大暑 | 処暑 | 秋分 | 霜降 | 小雪 | 冬至 | 大寒 |
日本の季節感と大陸のそれとはずいぶんと違いがあった事から、日本では二十四節気にプラスするように「雑節」と呼ばれる季節の移り変わりを表す日を設けています。
| 新暦月 | 2月 | 3・9月 | 3・9月 | 5月 | 6月 | 7月 | 四立の頃 | 9月上旬 | 9月中旬 |
| 雑節 | 節分 | 彼岸 | 社日 | 八十八夜 | 入梅 | 半夏生 | 土用 | 二百十日 | 二百二十日 |

さらにさらに日本には二十四節気それぞれをに三つに分けた「七十二侯」とうい節目もある事から、昔の日本人が季節の移り変わりに敏感で、自然とともに暮らしていたかが分かります。
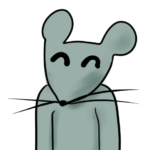
オリジナルに手を加えて最高のものをつくり出す日本人の柔軟性と感性の豊かさを、このような「暦・節目・季節感」の中にも垣間見ることが出来ますね!
春分の日を挟んだ前後3日間:春の彼岸(はるのひがん)
毎年3月18日~3月24日あたりに春の彼岸は訪れます。
| 彼岸の期間 | 名称 |
| 1日目 | 彼岸の入り |
| 2日目 | |
| 3日目 | |
| 4日目 | 春分の日・お中日 |
| 5日目 | |
| 6日目 | |
| 7日目 | 彼岸の明け |
一般的には仏教的な解釈をもとに”(死者の魂が)あの世からこの世に行き来できる期間”と信じられていて、お墓参りやご先祖様供養をする期間として定着しています。

お盆と同じようなイメージですね。
仏教用語。
- 死者の世界=「彼岸」
- 生者の世界=「此岸」
正確には『私たちが生きる苦楽や煩悩にまみれた世界(此岸)から、修行を通じ、悟りの世界(彼岸)を目指す』という考え方から来ています。
悟りの世界(彼岸)への修行は「六波羅蜜」と呼ばれていて、大雑把に言えば以下の表にある”6種類に分類された修行”のことです。

| 修行の名称 | 目指す事 |
| 布施・ふせ | 自分以外に施す事 |
| 持戒・じかい | 戒めをもって生きる事 |
| 忍辱・にんにく | 辛抱強く我慢する事 |
| 精進・しょうじん | 努力し励む事 |
| 禅定・ぜんじょう | 落ち着き動揺しない事 |
| 智慧・ちえ | 真理を学び見極める事 |
このように”修行”と言っても別段難しいわけではなさそうです。
ご自身の日々の『開運』のためにも、またご先祖様との再会の時期(彼岸やお盆など)に合わせて「六波羅蜜」の修行・・心がけてみるのもいいかもしれませんね。
なぜ彼岸に先祖供養をするの?
「春分の日・秋分の日」を中心に彼岸の期間が、『太陽が真東から昇り真西に沈む事』に関係していてます。

仏教ではいわゆる「西方浄土」と呼ばれる天国(極楽)のような世界が「西」にあると信じられていて、彼岸の頃は、あの世である彼岸とこの世である此岸が一直線となり、最も行き来しやすくなると考えられるようになりました。
この世に残された人々にとって手の届かない世界に旅立った”ほとけの世界”が最も近づく期間であるからこそ、日々の報告や感謝を込めて・・あるいは故人の残した努力や功績を長く忘れないために・・彼岸の時期は絶好の「ご供養時期」とされたのでしょうね。
因みに余談ですが、浄土は「西」にのみ存在するわけではないんです。ご存知でした?
| 方向 | 浄土名 | 如来(仏)名 |
| 北方 | 娑婆浄土 | 釈迦如来 |
| 東方 | 浄瑠璃浄土 | 薬師如来 |
| 南方 | 補陀落浄土 | 宝生如来 |
| 西方 | 極楽浄土 | 阿弥陀如来 |
| 中央 | 無 | 大日如来 |
このようにすべての方位・中心に仏はいらっしゃる・救いは存在しているという考え方が仏教にはあります。こんにちのように特に「西」が際立って解釈されるのは死後に待つ極楽浄土が「西方」とされたことに由来しているのでしょうね。
人は誰しも、健康で生きられ体の自由がきく頃は「仏にすがる」なんてことはしませんが、ひとたび病を得てしまったり老境に差し掛かると、それまでとはうって変わって諸々の「救済」を求めようとするものです。
「極楽浄土」は苦から解放された世界と信じられていますので、単に死者を弔い感謝を伝える期間の「彼岸」としてだけでなく、いずれ自分自身もお邪魔する世界、またそこに辿り着けるよう修行(六波羅蜜)に励む期間として「彼岸」が大切にされてきたというわけなんですね。
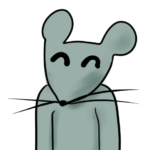
近しい仏様が(この世に)お戻りになって、私たちの日頃の不摂生・殺生・怠慢などをご覧に入れちゃったら恥ずかしいもんね(笑)
せめてその期間だけでもご供養を思い出し、修行に励んでおかなきゃって考えたのかなぁ~?

そうかもしんないね!
みなさん、日ごろからご先祖様と向き合ってらっしゃいますか?
春分を挟んだ「彼岸」は格好のご供養時期です。
いつも何かと忙しくされている方でも、無理のない範囲で先ずは近しい仏様から~思い出し~ご供養なさってみてはいかがでしょうか?

供養の極意は「忘れない事」「繋ぐ事」「感謝する事」。
儀式の中に安堵することなく、先ずは偽りのない心をお供えできるように・・努めてまいりましょう。
3月にまつわるその他の行事・イベント
立春から春分までの間:春一番(はるいちばん)

気象庁が解説する「春一番」の語源説によると、石川県能登地方・三重県などで「春一番」が用いられていた歴史があるほか、安政6年(1859)旧暦2月13日・現長崎県壱岐市の漁船が強風にあおられ転覆し、死者50名を出す大惨事を引き起こした、その南風を「春一」「春一番」を称した事が由来としています。

ベテラン漁師でさえ避けられなかった春先の強風・・現在の「春一番」は以下のように定義されているようです。
【春一番の定義】
- 時期=立春から春分の日まで
- 風向き=日本海側に発生した低気圧に向かって吹く南風
- 風の強さ=観測10分間平均:風速8m/s以上の風
- 気温変化=前日に比べ気温上昇が観測される事

春一番の風の強さの取り決めは関東や九州など各地域ごとに違っているんですって。
3月14日:ホワイトデー
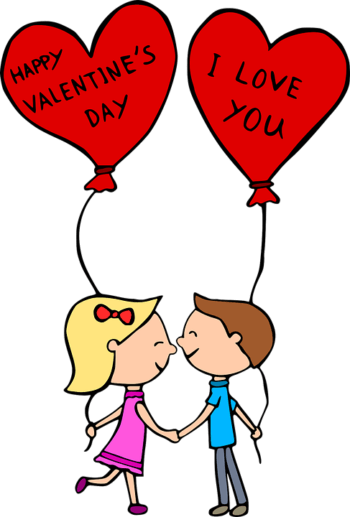
2月14日のバレンタインデーの”お返し(ありがとう)”を伝える日です。
そもそもバレンタインデーについて、発祥したキリスト教圏では、現在でも「男女の区別なく異性に日頃の感謝や愛情を伝える日」とされていますが、日本では「女性側から男性側へ好意をつたえる日」として広まったために、男性側からの返礼の日が独自につくられることになりました。
それがバレンタインデーより1か月過ぎた3月14日の「ホワイトデー」というわけなんですね。
ホワイトデーの発祥は諸説ありますが、概ねお菓子メーカーの便乗商法に由来しています。
- 不二家さん=1973年・お菓子での返礼「リターン・バレンタイン」
- 石村萬盛堂さん=1978年・キャッチフレーズ”君からもらったチョコレートを僕の優しさ(マシュマロ)で包んでお返しするよ”の「マシュマロデー」
- 全飴協さん=1978年・「キャンディを贈る日」

なおホワイトデーの”ホワイト”は・・
- ①石村萬盛堂さんのマシュマロに限定することなく、他業種にも販売のすそ野を広げる為に「ホワイトデー」に名称変更されたという説。
- ②全飴協さんの「辞典のホワイトの意味」に~白い砂糖やスイートといった解説~がある事にちなみ、若者の純愛、砂糖のような甘い関係をイメージし「ホワイトデー」としたという説。
この2説が有力なようです。

ね~父ちゃん!
おれ、ね~ちゃん2人と、かあちゃんからしかチョコもらったことが無いんだけど・・
チョコもらえなかった男の人はどうやってこの日を過ごせばいいのかな・・

そりゃ~もう
- ふて寝
- やけ食い
- 無視
からの~~
- 筋トレ
- イメトレ
- イケメン化
来年に向かって頑張るんだ!!ククク

ちぇ、結局最後はイケメンかよ~~
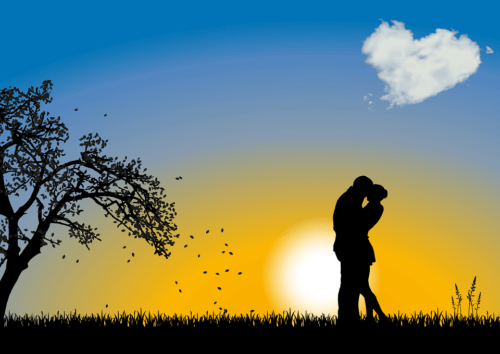
2月14日のバレンタインデーにチョコを送った女性は・・意中の男性から「お返し」や「デートのお誘い」があるといいですね♡
また、残念ながらチョコをもらえなかった多くの男性にも「モテ期バブル」やってきますようにと、祈っております♡
関連記事:「バレンタイン司教とバレンタインデーについて」
3月の花
長かった寒い季節は遠ざかり、色とりどりの花や新芽が地表や木々の先から”ひょっこり”と、顔をのぞかせてくれるようになります。
暖かな陽気に誘われて、上着の1枚を脱いで、たまの散歩を楽しんでみると、元気に咲き誇る花達に出会えることでしょう。
3月に見ごろを迎えてくれる素敵な花をご紹介します。
桜(さくら)

バラ科サクラ亜科サクラ属の落葉広葉樹。
現在では単に「お花見」と言えば、「桜の花見」が連想されるほど日本国民に愛されている花ですね。
そして日本人の多くは、単に「桜」と言えば、私たちの暮らしの身近な公園や河川敷に植えられている「ソメイヨシノ」の花を連想する事でしょう。
山肌に自生する種類から、社寺に古くから植えられている品種、品種改良がなされ近年になって植えられたものまで・・交配種を数えると400種を超えると言われる「桜」。そのすべてはご紹介できませんが代表的な品種に注目し、およその開花時期や花の特徴を表にまとめてみました。
お花見の参考になさってみてください。

| 桜の名称 | 開花時期 | 色 | 特徴 |
| 寒緋桜・カンヒ桜 | 1月下旬~2月上旬 | 濃い紫ピンク | 15℃が開花の合図・下向きの一重咲き |
| 河津桜・カワヅ桜 | 2月上旬~3月上旬 | 濃いピンク | 静岡県河津町にて発見。大輪の一重咲き |
| 江戸彼岸・エドヒガン桜 | 3月中旬~4月上旬 | 淡いピンク | 春の彼岸に見頃。長寿。小輪の一重咲き |
| 枝垂桜・シダレ桜 | 3月中旬~4月中旬 | 種類による | 枝が下に垂れる。一重咲き・八重咲様々 |
| 大島桜・オオシマ桜 | 4月上旬 | 真っ白 | 桜餅の葉はこの品種。大輪の一重咲き |
| 染井吉野・ソメイヨシノ | 4月上旬 | 淡いピンク | 見かける桜の8割。大輪の一重咲き |
| 山桜・ヤマ桜 | 4月中旬 | 淡いピンク | 日本固有種。若葉が赤っぽい。一重咲き |
| 西洋実桜・セイヨウミ桜 | 4月中旬 | 種類による | サクランボのなる桜。一重咲き |
| 八重桜・ヤエ桜 | 4月中旬~下旬 | 種類による | 八重咲き桜の総称。花びらが6枚以上 |
| 大山桜・オオヤマ桜 | 4月中旬~5月上旬 | 濃いピンク | 寒冷地でも育つ。大輪の一重咲き |
蒲公英(たんぽぽ)

キク科タンポポ属の多年草。
開花時期は3月~4月中旬にかけて。
花は一般的に黄色ですが白花もあり。
非常に生命力が強い植物で、地表からの大きさは約15センチ程度なのに、対する根の長さは最大で1メートルにもなるそうです。
コンクリートやアスファルトの小さな隙間にさえ根を下ろすことのできるタンポポ・・花が咲き終わると伸び出してくる「白い綿毛(冠毛)」は種子の部分で、ふわりと広がり始めると自然の風の力で何処ともなく飛翔し、新たな結縁の先を見つけて行きます。

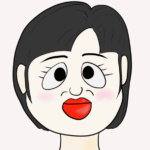
ふ~って、息を吹きかけて飛ばすの楽しいよね♥
タンポポは世界中で愛されるとても有名で一般的な植物ですので、各地域で名称についての語源が数多く伝わっています。ここでは、その一部をご紹介。
- タンポポの属名タラクサクム属(Taraxacum):ギリシャ語の「苦痛を癒やす」という意味。
- 英語圏ダンディライオン(Dandelion):元フランス語の「ライオンの歯」という意味。ギザギザしたタンポポの葉っぱがライオンの牙に例えられた。
- 英語圏ブローボールス(Blowball):球状の綿毛が壊れるように散っていく様に由来。
- フランス語ピサンリ(Pissenlit) :ベッドの中で”おもらし”をした円形がタンポポの形状と被ることに由来。(タンポポ茶などに利尿作用がある)
我が国での「タンポポ」の語源は以下の2種類が有名で・・
- タンポ説:拓本を採るときに墨をつけて叩く道具(タンポ)の形状が、花が咲き終えた後の「綿毛」に似ていることから「タンポ(の)穂」と呼ばれた。
- 鼓説:茎を切りその両側を細く切り裂くと「鼓」のように見える事から、鼓独特の「タン・ポン・ポン」の音にちなんだとする。(タンポポは江戸期には鼓草と呼ばれていた)
このように言い伝えられているそうです。
菜の花(なのはな)

アブラナ科アブラナ属の花の総称。
一般的にはアブラナの別名として用いられていますが、本来の意味は「食用の花」。
花の開花時期は地域ごとに違いがありますが、概ね2月中旬から5月いっぱいまで。
食用油を採取するための「菜の花畑」はもちろん、地域の花壇などでも積極的に植えられていると思います。
菜の花(アブラナ)は高さは40~80センチほどで直立し、花は4枚の黄色の花弁からなり、茎の上部に集中するように花を咲かせます。

概ねソメイヨシノの開花時期とも重なる事から、河川敷や大きめの公園などでは、地面に近い場所では「菜の花」が、高い枝に「桜」が咲き乱れるという”二重の花園”が演出される穴場も各地にあるそうですよ。
3月の魚
3月・・気温は上昇傾向を示しますが海水温的にはまだまだ冷たく、春の産卵期を控えたこの時期は、多くの魚介類は旨味が増し、脂ののった旬を迎えてくれますね。
眼張(めばる)
カサゴ目メバル科に属する近海魚。
体長:20~30センチ程度
一般的に「白・赤・黒」メバルの総称で、漢字の「眼張」の名の通り、体のバランスに対し”大きく張り出した目”が特徴。近海の防波堤などに生息している種類が「黒メバル」と呼ばれ、沖合に生息する種類を「赤メバル・沖メバル」と呼ばれています。
身は低脂肪の白身で癖が無くとても美味しい魚です。
調理方法としては定番の「お煮つけ」が一番ですが、唐揚げ、塩焼き、お刺身などでもご賞味いただけます。
メバルは日本列島どの地域にも生息していますが、春先の産地としては青森県・秋田県などが有名で、特に青森産の「ウスメバル」は大変美味で、築地市場などでは高値で取引されるのだとか。
お目々がキョロリとして愛嬌たっぷり、おまけに美味しいメバル君ですが、春にちなんだとても素敵な別名を持っています。
その名も~春を告げる魚~「春告げ魚」。
一般的に「春告げ魚」と言えば、ニシン・メバルを指すそうですが、地域によっても違いがあるそうで・・
東北・北海道は「ニシン」
関東・東海は「メバル」
瀬戸内・九州は「イカナゴ」
・・の事なんだそうです。
いずれにしても春先に水揚げされ、旬を迎える「お魚」としての意味に違いはなく、それぞれの地域・伝統に合わせた縁起物として「市場」を賑わせているそうです。
鰆(さわら)

スズキ目サバ亜目サバ科サワラ属の海水魚。
体長:80センチ~1メートルほど。
サワラの名は、ほっそりとした姿にちなんだ~狭い腹~を「サ・ハラ」と呼んだことに由来し、漢字で「魚」に「春」を当てるのは、主に瀬戸内海方面で産卵期(5~6月)を前に姿を現すようになる事にちなんでいます。
また大きさにより名称が変化する「出世魚」でもあり、
50cm未満「サゴシ」
60cm未満「ナギ」
60cm以上「サワラ」
と呼ばれているそうです。
サワラは新鮮な時は白身に見えますが、実は赤身魚に分類されます。身はやわらかく一見淡白に感じますが、噛むほどに独特の甘みが増し調理法を選ばない万能食材として人気があります。
召し上がり方としては何といっても「西京焼き(味噌焼き)」。
サワラの淡白さと、味噌の持つコクと塩気の相性が抜群で、サワラと言ったらの”定番メニュー”となっています。
その他にも「刺身」「塩焼き」「カルパッチョ」「船場汁」(時期ごとに水揚げされる安価な魚を放り込み、塩のみで味付けする汁物)などでも、おいしく頂くことが出来ます。
産卵を終えた夏場の時期を除けば、年中味の劣化を感じさせることの少ないサワラですが、地域によって旬(人気)に違いがあるそうで、西日本では春先、東日本では秋から冬にかけての「寒鰆」が好まれます。
味そのものを比べると脂のよく乗った「寒鰆」に軍配が上がりますが、大型に限定され、かつ水揚げ量も少ないことから、やはりサワラの旬は「春」にしておいた方が無難なようです。

食べやすくておいしい魚なので、「西京焼き」のようにあらかじめ下処理された状態で売られることも多いですが、加工品の多くは産地が外国産のものが大量に出回っています。
『国産食材』にこだわりをお持ちの方は裏の表示をよくご確認ください♡
3月の野菜
植物の芽吹きがいたる場所から聞こえてくる3月は、山菜をはじめ多くの野菜も旬を迎えてくれます。
蕗の薹(ふきのとう)

キク科フキ属の多年草。
一般的に煮物や炒め物で頂く、シャキシャキした歯ごたえがたまらないあの「フキ」の花の部分。
春先に出る若い花芽をフキノトウ(蕗の薹)と言います。
地域によって収穫時期にばらつきがありますが、概ね2~3月頃に時期を迎えます。
フキノトウの産地としては「愛知県」と「群馬県」が有名で、両県をあわせると全体の60%ほどの収穫となるそうです。
つくし・ぜんまいなどと並び春を告げる山菜として有名なフキノトウ、その独特の苦みが癖になるお味を「天ぷら」「おひたし」「和え物」などで頂いてみてはいかがでしょうか?
フキノトウの味の決め手は何といっても”鮮度”なんです。
フキノトウはとてもエグミ・アクの強い食材で(うまみ・風味とも言える)、採れたて新鮮なほどエグミ・アクが控えめで、時間が経つごとにそれらが増加してきます。
ですので鮮度の見極めのコツをご紹介しておきます。
- 花が開いていない・・小さく丸っこく見えるもの
- 正面からのぞき込む・・花が見えるかな?までがOK
- さわるとしまって(固く)感じる・・手にとれる場合のみお試しを
- 根元の切り口の色・・黒ずんでいない葉に近い色を選ぶ
新鮮なフキノトウを選び終えたら今度は下ごしらえです。
フキノトウのおひたしを作る場合などは”下茹で”をします。
【下茹でと保存について】
- お湯を沸かし熱湯に塩を入れます
- 熱湯にフキノトウを投入しお好みで茹でます(概ね2~3分)
- 落し蓋をしましょう
- 茹で上がったら素早く冷水にさらします
- 冷水に浸したまましばらくすると、熱とともに上手にアク抜きが完成します
- キッチンタオルなどで十分水気をふき取りましょう
- 保存する場合は料理用パックなどでなるべく空気を遮断し冷蔵庫へ
- 長期間の保存の場合は冷凍庫へ
- 解凍する場合は必ず自然解凍を!(せっかくの風味が逃げてしまいますので)
ご注意:もちろんですが「天ぷら料理」にはアク抜きは必要ありません。そのまま調理しフキノトウのもつ最大の長所、独特の春の味と香りを存分に楽しみましょう。
ビールにもお酒にも合うフキノトウ・・春の味覚として・・カンパ~イ!
春キャベツ

アブラナ科アブラナ属の多年草。
キャベツ自体は1年中収穫されていますが、前年の9月~11月頃に種をまき、翌春の3月~5月頃に収穫されるキャベツを特に「春キャベツ」と呼んでいます。
他の時期のものと違い葉がみずみずしくやわらかくなるのが特徴で、「千切り」などサラダ(生食)として食べると特に甘さを感じられるはずです。
キャベツは下の図のように収穫時期ごとに産地に特徴があるそうです。
| キャベツ | 冬キャベツ | 夏秋キャベツ | 春キャベツ |
| 産地名 | 愛知県 | 群馬県・長野県・北海道 | 千葉県・茨城県・神奈川県 |
キャベツに含まれる各種ビタミン類・ミネラル類・食物繊維などが”美容健康にいい”という話はよく耳にしますが、実はキャベツの効能はそればかりではないそうです。
キャベツの葉に多く含まれる「ビタミンU」は抗潰瘍性で胃腸の粘膜のただれを修復してくれる効果が見込めるそうで、お酒を飲む前などにキャベツをサラダとしていただいたり、「ビタミンU」が含有される市販の製剤などを前もって服用しておくと、胃腸の炎症などを防いでくれるそうです。
そして注目なのがキャベツに期待される「抗癌作用」で、豊富なビタミンCによる抗癌化作用はもちろん、アブラナ科の植物に多く含まれると言われている「イソチオシアネート」はがん抑制物質とされていて、近年の研究でも「ニンニク」・「カンゾウ」・「キャベツ」と、がん予防に貢献する食材として特に注目を集めています。
椎茸(しいたけ)

ハラタケ目キシメジ科のキノコ。
日本人の食文化にとって特になじみの深いキノコで、旬は秋のみと思われがちですが「春3月~5月」にも旬を迎えるそうです。
「シイタケ」は大きく「生シイタケ」と「干しシイタケ」に分類され・・
生シイタケは、主に「焼き」「天ぷら」「茶碗蒸し」「スープ」などに用いられ、風味豊かで肉厚な食感が楽しめる反面、鮮度が落ちやすく保存にはすこし不向きです。
干しシイタケは、主に「出汁」「つくだに」「煮物」などに用いられます。
生シイタケの産地としては「徳島県」「北海道」が有名で、干しシイタケは「大分県」が有名な産地となっています。
シイタケ・・生シイタケももちろんおいしいですが、シイタケは「干す」事によって長期間の保存が可能となるだけでなく、その香りも栄養素も格段にUPされることをご存知でしょうか?
| シイタケの成分 | 生シイタケ | 干しシイタケ |
| エネルギー | 18cal | 180cal |
| ビタミンD | 2μg | 17μg |
| カリウム | 280mg | 2100mg |
| 食物繊維 | 3.5ℊ | 14ℊ |
- エネルギー=約10倍
- ビタミンD=約8倍
- カリウム=約8倍
- 食物繊維=約4倍
この他の各種栄養素UPはもちろん、「レンチオニン」成分による香りのUP、「グアニル酸」増加によりうまみもUP!
さらに気になる”お値段比較”においても、一般的な生シイタケの価格を「100ℊ200~250円」と見積もり、干しシイタケを「100ℊ500~600円」とすると・・価格的には2~3倍の開きがあることになりますが、干しシイタケはその名の通り「乾燥品」、水で戻すと約4倍程度になります。
こうしてみると「あれ、案外干しシイタケもお得なの?」って感じませんか?
お料理の用途に合わせて使い分けるのはもちろんですが、長期間の保存が可能で、栄養素も香りもUPし、おまけに価格で比べても「戻し率」を考えると”お得”な干しシイタケ、毎日のお味噌汁や、たまの煮物などに・・備蓄してみてはいかがでしょうか?

干しシイタケを「戻す時」はご注意くださいネ。
料理に間に合わないからと急いで戻したり、温水を用いると凝縮された折角の香りが逃げ出してしまうかもしれません。
毎日のお味噌汁などをつくる場合は”前日の夜”から戻すようにしましょう。(理想は冷水5℃程度で10時間)
また、シイタケ表面の汚れについては水道水などで十分ゴミを取り除けばOK。ゴシゴシと強く洗い流さないでくださいね。
シイタケ栽培は基本的に無農薬(個々調べてね!)で行われますので、他の食品と違い残留農薬の心配をする必要が無いんです(ただし国内産に限る)。
冷水で、しかも十分な時間をかけ戻すと、「あれ、いつものと”お出し”かえた?」ってくらい違って感じます。
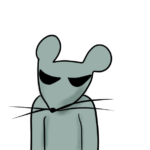
㊙:ど~~~~~してもお急ぎで「戻したい時」は、次の事をやってみてね!
- レンジ編:普通の煮物などをレンジする要領。水につけた干しシイタケを容器に入れラップして(500Wで3分くらい)。レンジ終了後もそのままで10分以上放置。
- 温水編:50~70℃程度の温水にシイタケを浸し、ラップをして1時間以上放置。
どちらも”ラップ(ふた)をしてシイタケを空気に触れさせない”のがコツ。
香りは随分飛んでしまうけど、お料理には間に合う。うっかり”戻し忘れ”した際などにやってみてくださいな(小声♥)
おいしいシイタケを余すことなく、おだしも果肉もあわせていただく・・ちょっとした工夫で毎日の料理がグンと味わい深いものになると思いますよ♡
まとめ

いかがでしたでしょうか。
当サイトのキャッチフレーズ『開運』が詰まったいろんな3月をご紹介してみました
名称・行事・縁起・花・誕生石・魚・野菜
知っている事も知らなかったことも含め、何気ない日常会話の豆知識などに、計画途中の旅行先の口実などに、本ページが少しでもお役に立ち、みなさんの長い人生の中で「春分・芽吹きの季節、3月」を、今までよりももっと楽しんでもらえる一助となりましたら幸いです。

